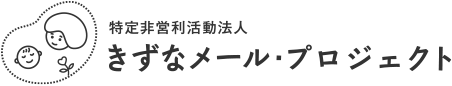「アンコンシャスバイアス」ってご存知ですか?/「学童期・思春期メッセージ」第16回編集会議開催報告
コンテンツチームの荻原です。
きずなメールは「テキストでつながり続けるセーフティネット」です。2024年11月24日現在、5万8856人の読者の方とつながり続けています。
より長くつながりつづけるために現在、18歳までの「学童期・思春期メッセージ」をブラッシュアップするための編集会議を、オンラインで月1回、開催しています。
第16回の12月10日は、6名の医師と、4名のきずなメールスタッフが参加しました。
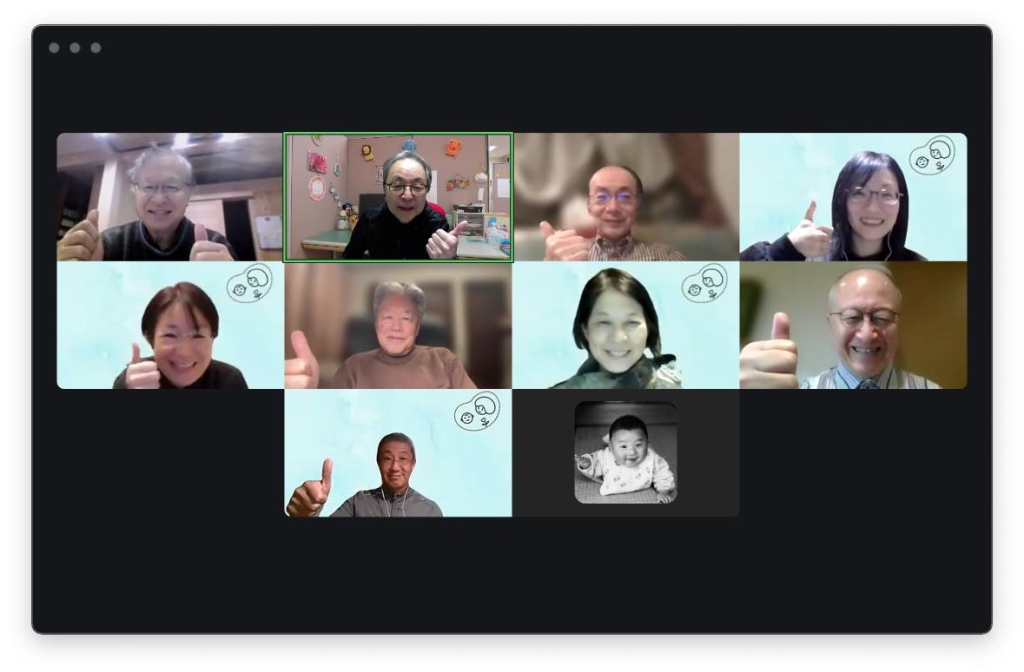
この学童期思春期メッセージは、段階を踏んで育てていく原稿です。
現在、第2段階のアップデートが終了しています。
どのような内容が追加されたかは、第13回編集会議開催報告をご参照ください。
今回の会議は、学童期、思春期を離れて、0~3歳のお子さんとそのご家族を対象とした「子育てきずなメール」の見直しについて議論を交わしました。
時代の変化によって「普通」「一般」の認識は改められていくものです。
今回はそんな、言葉の刷新や、推奨行動の変更などについての内容でした。
何が「一般的」な表現なのかは正確な答えはなく、どこまでやっても、絶対的な正解はないものですが、医学の世界の最新の認識などを医師たちに共有いただきながら、「より多くの方に届きやすそうな内容や言い方」へ向かって言葉が積み上げられていく、とても貴重な場に立ち会わせていただいています。
【コンテンツ担当の思索録】「アンコンシャスバイアス」ってご存知ですか?

アンコンシャスバイアス(unconscious bias)とは、何かを見たり、聞いたり、感じたりしたときに、「無意識に“こうだ”と思い込むこと」を指します。
例えば、
・血液型を聞くと、とっさに、“こんな性格だ”と思う
・赤いランドセルをみると、とっさに、女の子のものだと思う
・「親が単身赴任中」と聞くと、とっさに、父親のことだと思う
(一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所より参照)
など。言葉としては耳慣れない方もいるかもしれませんが、内容を聞いてみると「なんとなくわかる」と納得される方も多いのではないでしょうか。この「アンコン」が、令和7年度4月から、中学校の道徳の教科書に掲載されることが決まったとのことなので(7社のうち2社)、話題に上げてみたいと思います。
「アンコンシャスバイアス」は、脳の疲労をおさえるための「脳のクセ」とも言えるよう。
簡単に見つかる答えに、思考が偏ってしまうのです。
脳がクタクタにならないよう必ずしも悪いものとは言えない働きで、完全になくすことは難しいもの。
教科書では、どのように伝えているのでしょうか。
一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所のサイトで、実際の教科書の文面が一部見られるようになっていたので、見てみました。
以下のリンクより確認ができます。
https://www.unconsciousbias-lab.org/report/20240917/3006/
■思い込みに「気づく」という主題
先ほども述べたように、アンコンは完全になくすことは難しいものです。
「なくす」ことが難しいなら、どうして行けばいいのか。その向き合い方として、教科書の中では「気づく」ことを主題にしています。
まずは、アンコンとはどういうものなのかという「知識」。
アンコンがどのような弊害を生むのかという「リスク」。
アンコンに気付くためにはどのようにしたらいいのかという「コツ」。
実際のアンコンとはどのようなものなのかという「具体例」など。
こういった内容を伝え、アンコンの存在を知り、自分が無意識の思い込みの中にいるかもしれない、ということに気づくことが大切だという内容となっています。
■このアンコンが自分の可能性も狭めている
アンコンによって、人を嫌な思いにさせてしまったり、人から受けたアンコンで自分が嫌な思いをしたりすることはもちろん、その思い込みが自分に向いたらどうなるかについても同じくらい大きく取り上げているところが、印象的でした。
「どうせ自分にはできない」「○○の教科が苦手だ」などの思い込みが、自分自身の可能性や選択肢を狭めてしまうかも…。
可能性をどんどん広げていける中学生年代の子どもたちにとって、大切な視点だと感じました。
今回は「アンコンシャスバイアス」について紹介をしました。
学童期、思春期メッセージを制作する際にも、「学童期の子どもはこういう感じだ」とか「思春期の自分はこうだった」「親というのはこういうものだ」など、自分自身もきっと「アンコン」をもって見てしまっていることがあるのだと思います。
できる限りこのバイアスを乗り越えていくために、認識をいつも新たにしていきたいです。
何度も見直すこと、自分以外の様々な人々とのかかわりの中で作っていくこと、新しい知識や情報を取り入れていくこと、実際の子どもたちと出会っていくことなど、できるところから取り組んでいきたいです。
今回の編集会議で行われた、「より多くの方に届きやすそうな内容や言い方」について言葉を交わしていくことも、この乗り越えのひとつの方法だと思いました。今はこういう傾向があるだろう、を考えることは、そうでないものについて、常に思いを巡らせることになるからです。
「学童期・思春期メッセージ」は、フェーズⅢまで段階的に育てていく原稿。何度もこのアンコンを正すチャンスを得ることができるつくりなのだとも言えます。
最大限に活かして、フェーズⅢ原稿の作成に携わっていきたいと思います。(了)
5歳児健診ポータルサイトが公開されました/「学童期・思春期メッセージ」第15回編集会議開催報告
5歳児健診の助成開始を通して、発達障害を考える/「学童期・思春期メッセージ」第14回編集会議開催報告
バージョンアップで強化したポイント/「学童期・思春期メッセージ」第13回編集会議開催報告
「この年代は悩みがちでネガティブだ」という先入観/「学童期・
「いい依存」と「悪い依存」。大切なのは「支援とつながり続けること」/「学童期・思春期メッセージ」第11回編集会議開催報告
「体罰等によらない子育て」について/「学童期・思春期メッセージ」第10回編集会議開催報告
学童期思春期の「性」を、どんな言葉で伝えるか/「学童期・思春期メッセージ」第9回編集会議開催報告
年齢に応じた「生命の安全教育」/「学童期・思春期メッセージ」第8回編集会議開催報告
「マルハラ」ってご存知ですか?/「学童期・思春期メッセージ」第7回編集会議開催報告
災害という非常時に、平時からの「そなえ」としてのきずなメール/「学童期・思春期メッセージ」第6回編集会議開催報告
「こども大綱」ときずなメール事業/「拡充原稿」第5回編集会議開催報告
「希望の型」を原稿にも盛り込めないだろうか/「拡充原稿」第4回編集会議開催報告
「拡充原稿」第3回編集会議開催報告/コンテンツチームの思索録
「拡充原稿」第2回編集会議開催報告/コンテンツチームの思索録