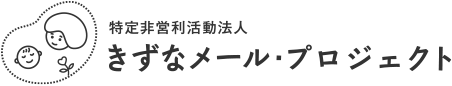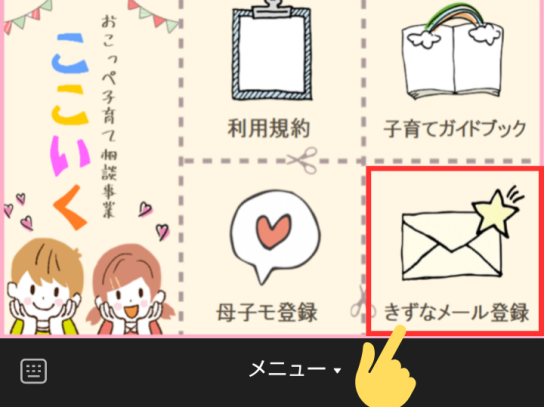「いい依存」と「悪い依存」。大切なのは「支援とつながり続けること」/「学童期・思春期メッセージ」第11回編集会議開催報告
コンテンツチームの荻原です。
きずなメールは「テキストでつながり続けるセーフティネット」です。2024年6月25日現在、5万7373人の読者の方とつながり続けています。
より長くつながりつづけるために現在、18歳までの「学童期・思春期メッセージ」をブラッシュアップするための編集会議を、オンラインで月1回、開催しています。
第11回の7月9日は5名の医師と、4名のきずなメールスタッフが出席しました。
 この学童期思春期メッセージは、段階を踏んで育てていく原稿です。
この学童期思春期メッセージは、段階を踏んで育てていく原稿です。
6~18歳のお子さんや保護者の方に向けたメッセージは、団体としても初の試み。
具体的には、3段階にわたってバージョンアップしていく計画となっています。
今は第2段階の準備について、検討を進めております。
いよいよ原稿制作も佳境です。
今回は、学童期思春期特有の問題についてご意見をいただいたり、実際の原稿を前に細かい表現や視点の置き所にまで話が及ぶ場面もありました。
ここまで11回の会議を重ねてきましたが、医師たちからはまだまだ新しい知見や情報をいただいたり、思いの深さについて改めて気づかされることも多くあり、毎回、この貴重な場に同席できることをうれしく思っております。
【コンテンツ担当の思索録】一番大切なのは「支援とつながり続けること」
 編集会議の場で、飲酒や喫煙、薬物依存についての話が出たときに、監修の医師から「依存症のことだったら」と、松本俊彦さんという医師がいることを教えていただきました。
編集会議の場で、飲酒や喫煙、薬物依存についての話が出たときに、監修の医師から「依存症のことだったら」と、松本俊彦さんという医師がいることを教えていただきました。
不勉強で私は知らなかったのですが、依存症について様々なメディアでお話されている先生で、ネット上に動画もたくさん公開されていたので、いくつか拝見してみました。
依存症だけにとどまらない、いくつもの発見がありました。
その中からふたつ紹介させてください。
■「依存症」とは、ちゃんと依存できていないということ
依存には「いい依存」と「悪い依存」があって、「いい依存」というのは、生活をよくするための依存なのだそうです。
夕飯時の晩酌とか、始業前のコーヒー一杯とか、それを頼ることで本人が活躍できているなら、その依存について誰もとめたりしない。
けれど、何かに依存した結果、本人が期待する結果と裏腹になっている場合は、「悪い依存」なのだと。
例えば、お酒を飲むことをいいところでやめたいのにやめられない。量がコントロールできなくて、次の日会社を休んでしまうというような場合がそれにあたります。
その状態について「これはちゃんと依存できていない状態」だと、松本俊彦先生はおっしゃっていました。
当事者目線の、やさしい言い方だなと感じました。
とくに薬物に関する依存症を患っている方の場合、医者に行ったら通報されるのではないかと、依存症を治したいと感じているのに病院へ行くことをためらう方もたくさんいる、とのことでした。
そのように、自分の状況について後ろめたさや否定的な思いを抱いているときに、依存そのものを肯定してくれて「あぁ、ただ依存の仕方がよくなかったんだ」と思わせてくれるような言い方は、まずは自分の状況を受け入れなければならないはじめの一歩を踏み出す時に、とても心強い言葉だと感じました。
肯定の言葉で依存症を語り、「いい依存」に導いていくやり方は、ほかの困りごとに対しても、応用できることなのかもしれないと感じました。
■大切なのはやめつづけることではなくあきらめずに支援から離れないこと
依存症の治療において大切なことは、「やめつづけること」ではなく「支援から離れないこと」なのだそうです。
「依存症が治る」ことがゴールだとすれば、「やめつづけること」はとても大切なことに思えますが、それよりも「支援とつながり続けること」が大切だというのはどういうことなのでしょうか。
松本俊彦先生は、「やめようと思って失敗する経験を、何度も繰り返して、ある時にふっといい流れに乗れてやめられたという人がたくさんいる。そういう方が身近にいる人ほど、すんなりやめられている印象がある」というようなことをおっしゃっていました。
これは私の考えたことですが、これは「やめられないことを否定しない」ということではないかと感じました。
やめたくてもやめられなくて病院に来るのだから、やめられないことは当然で、「やめつづけること」は、苦しい状況のはずです。
苦しいことをずっと続けられるようにするのではなく、もし続けられなくて自分を責めたり絶望したりすることがあっても、似た思いを味わってきた方々や、理解者の方々とつながりつづけて、何度でもやり直せばいい、ということのように感じました。
「依存症が治る」ことがゴールではなくて「生き続けること」の方が大切…と言葉でいうのは簡単ですが、私なりにそんなことを受け止めました。
「やめつづける」ことにこだわって気を張り詰めていると、時によくないことを招いてしまう。
それよりも、「ゆるやかにつながりつづけること」。
依存に限らず、人は誰でも、孤独や疎外を少なからず感じていて、時にそれが世界のすべてのように思えてしまうことがあるのだと思います。
でも、実際には、それだけが世界ではない。他者とつながりつづけることは、自分自身をセーフティネットの中に招き入れることかもしれません。
令和4年度の不登校児童数、いじめの認知件数は、過去最多だったそうです。
学童期思春期にあるお子さんたちができるだけ安心安全な環境で過ごしていくための内容として、「SOSの出せる力を育てること」や「出しやすい環境を保護者が心がける」こととともに、つながりあった手をどうか離さないでいてほしいことも、伝えていきたいと感じました。(了)
「体罰等によらない子育て」について/「学童期・思春期メッセージ」第10回編集会議開催報告
学童期思春期の「性」を、どんな言葉で伝えるか/「学童期・思春期メッセージ」第9回編集会議開催報告
年齢に応じた「生命の安全教育」/「学童期・思春期メッセージ」第8回編集会議開催報告
「マルハラ」ってご存知ですか?/「学童期・思春期メッセージ」第7回編集会議開催報告
災害という非常時に、平時からの「そなえ」としてのきずなメール/「学童期・思春期メッセージ」第6回編集会議開催報告
「こども大綱」ときずなメール事業/「拡充原稿」第5回編集会議開催報告
「希望の型」を原稿にも盛り込めないだろうか/「拡充原稿」第4回編集会議開催報告
「拡充原稿」第3回編集会議開催報告/コンテンツチームの思索録
「拡充原稿」第2回編集会議開催報告/コンテンツチームの思索録