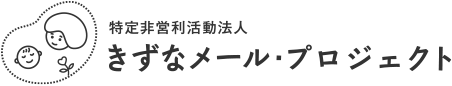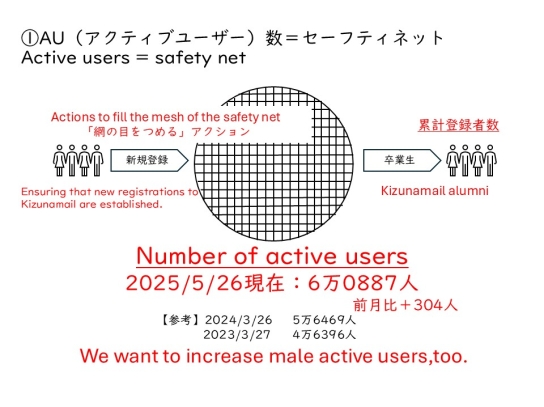「パートナー」「パパ」という表記の違いについて/子育てにおけるGender equalityを促すマタニティきずなメールRP⑧
コンテンツチームの荻原です。
妊娠期の「マタニティきずなメール」と、子どもが生まれてからの「子育てきずなメール」で構成される私たちの「きずなメール事業」では、年に一度、原稿を最新の状態に保つためのリニューアル作業を行っています。
どちらのコンテンツも医師や管理栄養士による監修を受けており、監修の専門家によるファクトチェック、読者から届いた声の検討、また、妊娠出産、子育ては時代によって変化しますので、その変化などに対応しています。
今年は様々な条件が重なり、例年よりも規模を大きくし、新たな視点を追加して「マタニティきずなメール」のリニューアルを行うこととなりました。
この大規模なリニューアルを「マタニティきずなメールリニューアルプロジェクト」として、こちらで進捗状況を報告しています。
ブログのタイトルにある「マタニティきずなメールRP」とは、「マタニティきずなメールリニューアルプロジェクト」を指しています。
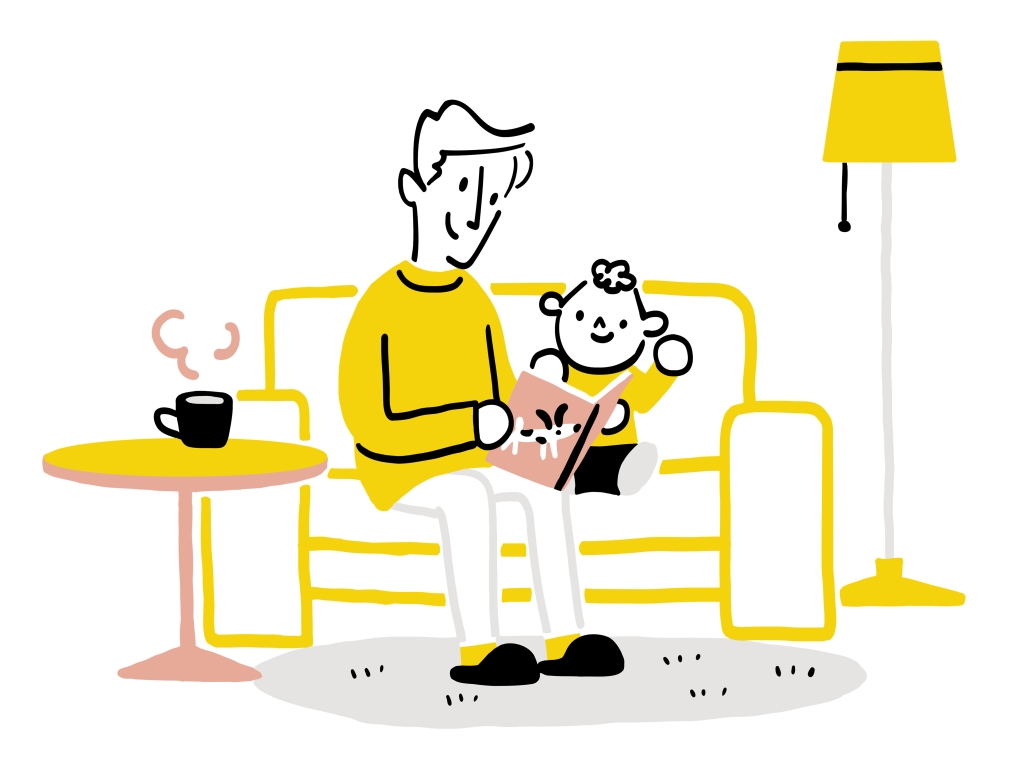
リニューアルプロジェクトは大きく分けて2つの時期に分かれています。
ひとつ目が「プレ・リニューアル期(団体内部でできることからやってみる)」、
ふたつ目が「メイン・リニューアル期(団体外部の意見を聞きながらやってみる)」です。
現在は「メイン・リニューアル期」にあたり、外部とのかかわりを大切にしています。
その一環として、6月より、団体外部の方に原稿を読んでいただき、そのフィードバックをもらう活動を進めています。
現在6名の方に読んでいただき、いただいたフィードバックを元にヒアリングをさせていただいているところですが、
自分たちだけでは気づくことのできなかった視点をたくさんいただいています。
「ジェンダーイコーリティ」に関連する視点でもたくさんいただいておりますが、まずはここがメインの視点なので、今日はこちらに関するフィードバックをご紹介したいと思います。
「パートナー」「パパ」という表記の違いについて
・「パパ」「父親」は統一したほうがいい
・全体的に『パートナー』とぼかした表現をしているのに、『ママ』や『パパ』になると押し付けられているように感じられました。
・同性同士とか、籍は入れていない男女でも。相手が妊婦できずなメール受け取る人は「父親」「パパ」になりたい思いあるのでは。パートナーとあえて書かなくてもいいかも
・パートナーがいる前提なのが気になる。
・ひとり親への配慮から、パートナー用と分けるのもいいのでは
皆さんはどのような印象を抱いたでしょうか?
一筋縄にはいかないな、というのがコンテンツチームの印象です…
こちらも関連する内容を書いています↓
「父親も育児当事者」を進めると「ひとり親」から遠のくか/子育てにおけるGender equalityを促すマタニティきずなメールRP⑥
きずなメールはママもパパも同じように読める原稿を目指しています。
それゆえに生まれるつまづきや葛藤もありますが、逆に言うと、だからこそつまづける、葛藤できるとも言えます。
日々よりよい原稿、あり方を模索していく中で、これから形は変わるかもしれません。
でも今は、この原稿だからこそ生まれる葛藤の中に身を投じ、考えつくせるところまでは一度、やってみたいと考えています。
それに、少しずつ違う環境や状況の中で妊娠や出産に向かう人々が、同じものを読むことができるって、なんだか素敵な感じがするのです。
「すべての人」とは到底言えないけれど、少しでも多くの人が一緒に読める、に挑戦しています。(了)
「父親も育児当事者」を進めると「ひとり親」から遠のくか/子育てにおけるGender equalityを促すマタニティきずなメールRP⑥
Gender equalityと性の多様性を「一緒に」考えてみる/子育てにおけるGender equalityを促すマタニティきずなメールRP⑤
プレリニューアル原稿完成しました/子育てにおけるGender equalityを促すマタニティきずなメールRP④
「ママ偏り」のある表記の調整/子育てにおけるGender equalityを促すマタニティきずなメールRP③
妊婦さんがお酒を控えているとき、飲みたい夫はどうする?/子育てにおけるGender equalityを促すマタニティきずなメールRP②
【進行中】子育てにおけるGender equalityを促す/マタニティきずなメール・リニューアル・プロジェクト①2024年11月
子育てにおけるGender equalityとは? 「きずなメール基金」による「マタニティきずなメール・リニューアル・プロジェクト」を開始しました。